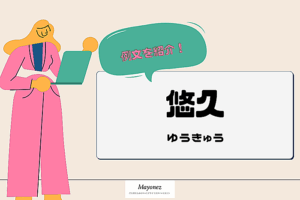
「悠久」の意味や例文を紹介|漢字の語源や「永遠」との違いは?
皆さんは悠久という言葉の響きから、どんな意味のイメージが湧くでしょうか。何かとてつもなく永い年月を思い浮かべるのではない...
更新日:2025年03月05日
ビジネスの場できわめてよく目にする「決裁」という用語ですが、実は誤った使い方をしている人も多い用語です。似た意味をもつ「承認」「稟議」、誤変換の多い「決済」についても併せて整理しています。本稿を読んで「決裁」を正しく使えるビジネスパーソンを目指しましょう。
目次
権限を持っている上位者が、部下の提出した案の可否を決めることが「決裁」ですが、「決裁」する対象事項案が上位者により可と判断されることを、「決裁がおりる」と表現します。 「おりる」を漢字で表現する場合は「下りる」という漢字になります。 もともと「下」という漢字には「上から下に移動させる」という意味があり、空間的な上下に加えて、身分のような上下関係における概念的な「上から下への移動」の意味があります。 上位者に対しお諮りしていた事案の可否判断が、部下に対して示されたということで「上から下」という方向性が明確になります。 例) ・滞っていた決裁がようやく下りたので、これで関係者合意を前提としてプロジェクトに着手することができる。 ・決裁が下りれば、この案件は半分完了したも同然です。それくらい本案件の決裁手続きにはてこずりました。

「とる」という語には「いろいろな方法で自分のものにする」という意味が含まれています。決裁の起案者は自分自身の案を、上司に可と判断していただくために案件説明や資料作成に注力します。最終的に「可」という判断を引き出すことができれば、それはすなわち自分自身の案件推進が認めてもらえたということになります。「決裁をとる」という主体的な活動の結果がこちらに表れています。 例) ・本件は会社の方向性を大きく変えるものであるので、しっかりと決裁をとってから案件推進する必要があります。 ・個別に決裁をとるとそれぞれ3,000万円以下の案件となるが、いずれも相互に関連した大きな一つの案件と考えると合計で1億円を超える契約金額となるため、部門長決裁をとる必要があると考えます。
「仰ぐ」には「上をみる、見上げる」という意味から派生し、「教え、助力を求める、請う」という意味が含まれます。権限を持つ上位者に対して、本案件の可否判断を請うことは正しい案件の進め方です。「決裁を仰ぐ」場合には、上席に対し可否判断をゆだねているということになります。 例) ・人事異動・昇進、契約の締結など、組織の決裁を仰ぐあらゆる事柄に稟議書が使われます。 ・3億円以下の案件であっても、場合によっては社長のご決裁を仰ぐ必要があります。

部下から上がってきた企画案や契約案について、決裁権限を保有する上位者はその可否を決定する必要があります。決裁権限保有者からみた可否の決定が「決裁する」という行為になります。可否を決定することですので、可の場合も否の場合も決定を下すことを「決裁する」と表現します。 例) ・契約金額が3,000万円以下であれば、部長が決裁します。 ・今週中に契約書一式を揃えることができれば、来週いっぱいで決裁することは可能です。

決裁に関連する用語の理解が深まったところで、実際の決裁の手順と方法を確認しておきます。決裁の細かいルールは各組織、企業により異なりますが、大まかな流れは変わりません。 流れとしては次のとおりです。 決裁起案:担当者により決裁を起案する ↓ 決裁回付:決裁を関係者へ回して承認してもらう ↓ 決裁完了:決裁権限者により承認された決裁書が決裁エビデンスとして保管される
担当者は職務分掌に応じて、担当業務に関する対応案、契約案、支払案を決裁書の形に整理して起案します。この際、決裁書を確認した上位者が速やかに可否を判断できるように工夫する必要があります。
| 工夫点 |
|---|
| 誰が/いつからいつまで/何のために/なにを/どのように/いくらくらいかけて対応するのか、5W1Hの観点で簡潔に整理する |
| 決裁内容に関連する諸書類は、決裁回付と一緒に確認できるよう別添添付する。とりわけ、契約書など公的書類については、決裁回付前に専業部署(具体的には法務部など)の確認を完了させておく |
| 決裁が契約や支払いなど金額に関連した事項である場合は、年間あるいは特定期間の予算の範囲内であることを専業部署(具体的には経理部や財務部など)の確認を完了させておく |
| 職務分掌及び決裁権限を事前に確認し、必要書類が滞りなく必要部署、担当者へ回付されるよう事前に案内、必要であれば個別に事前説明を実施する |
職務分掌および決裁権限に応じ、組織内のどなたに決裁書を承認いただくか決まります。速やかに決裁していただくためには、決裁書回付ルートのどこかで停滞することがないようにその進捗を確認する必要があります。 必要な承認者が外出、長期出張あるいは休暇取得されている場合は、決裁書回付に時間を要することになります。事前にスケジュールを確認しておくと場合によっては事後説明で対応できる場合もあります。また、決裁回付に必要な時間を確保して、発注やプロジェクト開始などの後続スケジュールを策定することも必要になります。 決裁者を含め承認いただく方には、事前に決裁内容をご説明しておきましょう。よほどしっかりした資料でも、書類を読んだだけで内容を正しく把握できる方は稀です。とりわけ決裁者が役職の高い方の場合、現場業務についての補足が必要となります。
記載されている内容は2018年02月16日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。
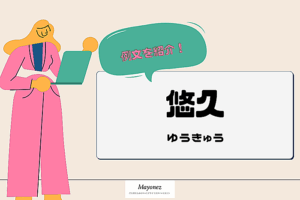
皆さんは悠久という言葉の響きから、どんな意味のイメージが湧くでしょうか。何かとてつもなく永い年月を思い浮かべるのではない...

いまさら意味を聞けないカタカナ語のひとつに、「ビバレッジ」があります。日常生活で使うことは少ないですが、意外と目にする機...

麻雀は世界中で広く遊ばれているテーブルゲームです。古い歴史があるため、麻雀で使う言葉が日常会話で使われることもしばしばあ...

「セパレート」ってそもそもどういう意味?もともと英語の「separate」という単語からきています。もともとの「sepa...

いつのまにか、使われなくなった「父兄」という言葉。なぜ使われなくなったのでしょう。父兄という言葉が生まれた背景とともに考...

履歴書の「趣味特技」欄で採用担当者の心を掴めないかと考えている方もいるのではないでしょうか。ここでは履歴書の人事の...

いまいち難しくてなかなか正しい意味を調べることのない「ご健勝」「ご多幸」という言葉。使いづらそうだと思われがちです...

「ご査収ください/ご査収願いします/ご査収くださいますよう」と、ビジネスで使用される「ご査収」という言葉ですが、何...

選考で要求される履歴書。しかし、どんな風に書いたら良いのか分からない、という方も多いのではないかと思います。そんな...

通勤経路とは何でしょうか。通勤経路の届け出を提出したことがある人は多いと思います。通勤経路の書き方が良く分からない...