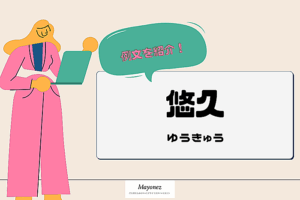
「悠久」の意味や例文を紹介|漢字の語源や「永遠」との違いは?
皆さんは悠久という言葉の響きから、どんな意味のイメージが湧くでしょうか。何かとてつもなく永い年月を思い浮かべるのではない...
更新日:2025年03月05日
普段何気なく使っている言葉の意味を、実は知らずに使っている時があるかもしれません。時としては間違った意味として捉えられることもあります。ここでは「余韻に浸る」の意味や、類義語や用例を紹介します。あなたの「余韻に浸る」の使い方は正しいでしょうか。
1つ目の例文は「昔を思い出して余韻に浸る」です。過去の思い出や過去の輝いていたときのことを思い出して、感傷的になったことのある方も多いのではないでしょうか。 「高校生のときに部活でインターハイに出場した」「大学生のときの文化祭の実行委員では徹夜で仲間と準備した」など、過去の楽しかった思い出を思い返すことは、たびたびあるのではないでしょうか。
2つ目の例文は「余韻に浸っている暇はない」です。具体的な例文として、「勝利の余韻に浸る間もなく、次の試合が始まる」を挙げます。 この場合に「余韻に浸る」は、楽しみ、興奮などが継続しているという意味合いの物です。その意味合いの言葉が「余韻に浸る間もなく」という言葉に変わると、意味も変わってきます。 大きく変わるということではなく、楽しみ、興奮などを継続したいがその暇がない、といった意味合いになります。
3つ目の例文は「映画を見た後しばらく余韻に浸っていた」です。日常生活において、使われやすい例文です。 こちらの用例も、いまだに感動もしくは楽しさが本人の中で継続されているという意味合いです。映画の良いシーンを思い出して感動に浸る、興奮が冷めないといったことは多いでしょう。この一文からはそのような様子がうかがえます。
4つ目の例文は「素晴らしい演奏の余韻に浸る」です。こちらの「余韻に浸る」は音の響きを楽しむといった意味合いを含んでいます。 観客として、素晴らしい演奏を聞いた人が、その音の響きが残るホール内の様子を存分に堪能している様子が伺えます。音の響きを味わう、楽しむ、残響を楽しむ、といった意味合いで使われており、直接的な表現のために意味がとらえやすいものでしょう。

続いて、「余韻に浸る」の類義語を確認していきます。「興奮冷めやらぬ」「余韻が残る」「余剰を味わう」の3つの類義語について説明します。 微妙なニュアンスの違いや、使い分けについても認識できるようになりましょう。
1つ目の類義語は「興奮冷めやらぬ」です。素晴らしい映画や演奏を堪能した後に、感動や興奮を覚え、それが一定時間続くことを指します。 「余韻に浸る」という表現と比較すると、「興奮冷めやらぬ」というフレーズの方が、その人の熱量が大きく感じられます。「余韻に浸る」はどこか、落ち着いた様子も含む言葉のため、そのような若干の違いがあります。
2つ目の類義語は「余韻が残る」です。「余韻に浸る」と同様に「余韻」という言葉が使われているフレーズです。 「浸る」には「つかる、何かの境地に入る」という意味があり、「残る」には「後にとどまる、後々まで消えずにいる」という意味があります。 ほぼ同様な意味ですが、若干のニュアンスの違いが感じられることでしょう。
3つ目の類義語は「余剰を味わう」です。「余剰」には「必要分を除いた残り。剰余。余り」という意味があります。 「余剰を味わう」にも、「心に残ったことを噛みしめる」という意味があります。「余韻に浸る」の代表的な類義語です。

記載されている内容は2017年11月29日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。
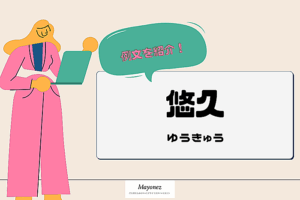
皆さんは悠久という言葉の響きから、どんな意味のイメージが湧くでしょうか。何かとてつもなく永い年月を思い浮かべるのではない...

いまさら意味を聞けないカタカナ語のひとつに、「ビバレッジ」があります。日常生活で使うことは少ないですが、意外と目にする機...

麻雀は世界中で広く遊ばれているテーブルゲームです。古い歴史があるため、麻雀で使う言葉が日常会話で使われることもしばしばあ...

「セパレート」ってそもそもどういう意味?もともと英語の「separate」という単語からきています。もともとの「sepa...

いつのまにか、使われなくなった「父兄」という言葉。なぜ使われなくなったのでしょう。父兄という言葉が生まれた背景とともに考...

履歴書の「趣味特技」欄で採用担当者の心を掴めないかと考えている方もいるのではないでしょうか。ここでは履歴書の人事の...

いまいち難しくてなかなか正しい意味を調べることのない「ご健勝」「ご多幸」という言葉。使いづらそうだと思われがちです...

「ご査収ください/ご査収願いします/ご査収くださいますよう」と、ビジネスで使用される「ご査収」という言葉ですが、何...

選考で要求される履歴書。しかし、どんな風に書いたら良いのか分からない、という方も多いのではないかと思います。そんな...

通勤経路とは何でしょうか。通勤経路の届け出を提出したことがある人は多いと思います。通勤経路の書き方が良く分からない...