
根性がある人の10の特徴・根性がある人になる方法
「根性」とは、一体どのような意味なのでしょうか。また「根性がある人」とは、どのような人なのでしょうか。このページでは「根...
更新日:2025年03月05日
物を数える時、その単位に何をつけつけかるかか迷ったことはありませんか。物の数え方はシチュエーションによって複雑に変わります。学校や会社、家庭で身近な机、テーブルの数え方も五種類以上あります。今回は、その机の数え方を基本の三種類を中心に紹介していきます。
目次

次に、机の種類別・用途別の数え方を明記していきます。
一般の家庭で食事をするための机である食卓、ダイニングテーブルの数え方は「一脚(きゃく)」です。同じ食事をする机でも、脚の低いちゃぶ台の数え方は「脚」でも間違いではないのですが、「一台」と数える方が落ち着きます。 これは明確に書かれた文書等はありませんが、「脚」が使われる場合はすらっとした細長い脚がついた机が多いです。思い浮かぶのは宮殿などに調度されている瀟洒な脚のついた机などです。「台」はどっしりとした太い脚の机に使われています。一般家庭の日本間に置かれている背の低い座卓は「台」です。このニュアンスによる使い分けは、日本人が持って生まれた感覚で自然とできているようです。
さらに食事をする目的の机でも、レストランなどに多い、囲むようなテーブルの数え方は「卓」が使われています。食事をする用途ではありませんが、「卓を囲む」机であるマージャン卓も「一卓」と数えます。 脱線しますが、レストランやホテルでの結婚式場、宴席でよく使われる「席数」とは机の数ではなく、「座席」つまり「椅子」の数のことです。
学校や家庭の学習机の数え方は「一脚」ではなく、「一台」です。また、多目的教室や大学の講義室などで使われる長机も「一台」と数えます。 先に「ダイニングテーブル」の項目で、すらっとした脚の机は「脚」、どっしりした脚の机は「台」という数え方と書きました。現在の学校で使用されている学習机は、パイプ製のすらっと細長い脚をしていますので、疑問に思われる方もいらっしゃるでしょう。 これは、昔の机はすべて木で作られており、脚も四角くがっしりとした造りのものでした。その名残で「台」という数え方が用いられていると考えられます。また、学習机は大きな平たい面を台で支えているものとして考えられているからだという説もあります。
事務机は学習机と同様の考え方・とらえ方として、「一台」と数えます。 会議やセミナーなどで使われる、脚を折りたたむことができる長机の数え方は「一枚」です。助数詞「枚」は、薄い平たいものを数えるときに使われます。机も、脚を折りたたんだものは薄い一枚の板になることから「枚」が使われます。また、細長いものを数えるときに使われる「一本」を用いる場合もあります。
一般的にはあまり馴染みがありませんが、読経のときに経文を載せる経机の数え方は「一前(ぜん)」です。また、厳密には机ではありませんが、お座敷など畳に座ったときに、座布団や座椅子の横に置かれているひじかけ「脇息(きょうそく)」も「一前」と数えます。
文化財に相当する机の数え方は「一基(き)」です。「基」には建造物の土台や物事の礎という意味が含まれています。助数詞としては「動かないもの」を数えるときに使用します。机は動かせますが、文化財となる机は実際に机として使用するものではありません。 博物館などで展示されたり、大切に保管されているものですので、「動かないもの」として扱われ「基」を用います。また同じ「き」と読む「机」という漢字を使うこともあります。文化財の机以外で「基」を用いた数え方を使う机は、公園などに固定設置されているテーブルなどがあります。これも「動かない」机ということで「一基」と数えます。
家具屋ではテーブル、椅子、箪笥など、多種の家具をまとめて数える場合が多いです。そんなときは「テーブル一台、椅子一脚、箪笥一竿」とそれぞれの助数詞をつけることはせず、「テーブル、椅子、箪笥まとめて三点」と言うように、「点」を使う数え方をします。

冒頭で外国の方には難しい日本語での物の数え方と書きましたが、日本以外でもこの助数詞にあたる言葉はアジア圏の中国語・韓国語などに存在します。日本語の助数詞は中国語に由来していると考えられています。中国語では、物を数えるときに数字の後に「量詞」(リヤンツー liàngcí)をつけて数えます。これが日本語の助数詞にあたるものです。 机を数えるときは「张(Zhāng)」(帳)を用います。「张」は広い面を持っているものを数えるときに使用します。
記載されている内容は2017年09月29日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。

「根性」とは、一体どのような意味なのでしょうか。また「根性がある人」とは、どのような人なのでしょうか。このページでは「根...

カフェやファミレスで気軽に楽しめる一品としてすっかり定番となったピザ。日本では手で持って食べるのが一般的ですが、では、海...

申し送りをする際、どのような事項を伝えればいいのかわからないという人はいませんか。この記事では、申し送りの目的や伝えるべ...

取引先や従業員に贈答品を贈った場合は、経費に計上できるのでしょうか。本記事では贈答品やプレゼントの勘定科目や経費で計上す...
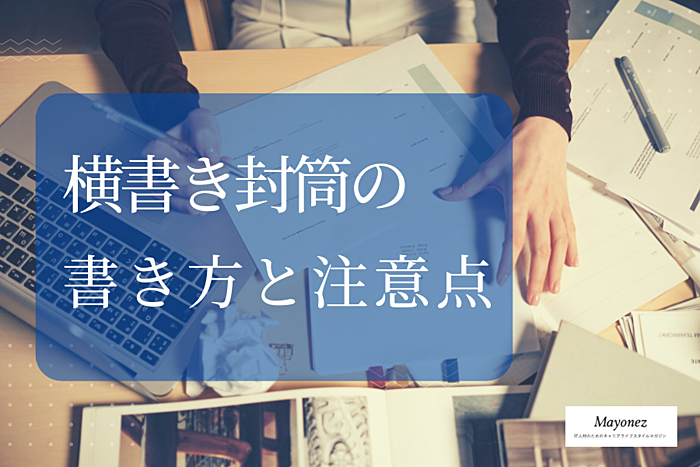
封筒に住所などを横書きするときの注意点をご存知でしょうか。この記事を読むと適切なマナーを守りつつ、一般的にビジネスシーン...

履歴書の「趣味特技」欄で採用担当者の心を掴めないかと考えている方もいるのではないでしょうか。ここでは履歴書の人事の...

いまいち難しくてなかなか正しい意味を調べることのない「ご健勝」「ご多幸」という言葉。使いづらそうだと思われがちです...

「ご査収ください/ご査収願いします/ご査収くださいますよう」と、ビジネスで使用される「ご査収」という言葉ですが、何...

選考で要求される履歴書。しかし、どんな風に書いたら良いのか分からない、という方も多いのではないかと思います。そんな...

通勤経路とは何でしょうか。通勤経路の届け出を提出したことがある人は多いと思います。通勤経路の書き方が良く分からない...