
「就活」と「起業」を選ぶために考えること
大学卒業後、または専門学校、高等学校を卒業したあと、就職活動を行うというスタイルが一般的です。ですが、必ずしも就職活動を...
更新日:2025年10月29日
「毎日仕事はしているけど、本当にこれが自分のやりたいことなのだろうか?」「このままでいいのか、将来が漠然と不安だ」。 そんな悩みを抱える社会人の方は少なくありません。やりたいことがわからない状態は、決して特別なことではな […]
目次

「毎日仕事はしているけど、本当にこれが自分のやりたいことなのだろうか?」「このままでいいのか、将来が漠然と不安だ」。

学生時代は夢や目標があったのに、社会人になってから急にやりたいことが見えなくなってしまうのはなぜでしょうか。その背景には、社会人特有の3つの原因が考えられます。
日々の仕事やタスクに追われる中で、自分のキャリアについてじっくり考える時間を確保するのは難しいものです。目の前の業務をこなすことで精一杯になり、いつの間にか「自分は何をしたいのか」という根本的な問いから目をそむけてしまいがちです。
思考する余裕を失うことで、現状維持が最も楽な選択肢となり、キャリアの迷子状態に陥ってしまいます。「30代なら安定した企業にいるべきだ」「この年齢で未経験の職種に挑戦するのは無謀だ」といった、周囲の価値観や社会的なプレッシャーも大きな要因です。
自分の内なる声よりも、「こうあるべき」という他人の物差しでキャリアを判断してしまうと、本当に自分が望む道から遠ざかってしまいます。この「べき論」が、自分の興味や関心に蓋をしてしまうのです。これまで培ってきたスキルや経験を活かせる仕事を選ぶのは、合理的で安全な選択です。しかし、それに固執しすぎると、新しい可能性に目を向ける機会を失います。
重要なのは、「できること」と「本当にやりたいこと」は、必ずしもイコールではないという点です。この二つを混同してしまうと、自分のキャリアの選択肢を無意識に狭めてしまい、やりがいを感じられないまま仕事を続けることになります。
やりたいことを見つけるための第一歩は、自分自身の内面と向き合うことです。漠然とした不安の正体を突き止めるために、まずは思考や感情をアウトプットし、客観的に見つめ直すことから始めましょう。
「やりたいことがわからないなんて、自分はダメだ」と自己否定する必要は全くありません。まずは「自分は今、キャリアに迷っていて、やりたいことがわからない状態なんだ」と、ありのままの自分を認め、受け入れることが重要です。
この認識が、次への一歩を踏み出すためのスタートラインになります。不安や焦りを感じるのは、あなたが真剣に自分の人生と向き合おうとしている証拠なのです。頭の中だけで考えていると、同じ思考がループしてしまいがちです。そこでおすすめなのが、思考を「見える化」する作業です。
アウトプットを通じて自分の思考を整理していくと、漠然としていた不安の正体が少しずつ見えてきます。

不安の正体が整理できたら、次に行うのは徹底的な自己分析です。自分自身の価値観、強み、弱み、興味を深く理解することで、キャリア選択におけるブレない「軸」を確立することができます。この軸こそが、キャリア迷子から脱出するための羅針盤となります。
仕事選びにおいて、自分が何を最も大切にしたいのかを知ることは非常に重要です。以下の質問にじっくりと答えてみてください。
自分の強みや弱みは、過去の経験の中に隠されています。「モチベーショングラフ」を作成するのは非常に有効な方法です。横軸に時間、縦軸にモチベーションの高さを取り、これまでの人生(学業、部活、アルバイト、仕事など)を振り返りながら、モチベーションの浮き沈みをグラフにしてみましょう。
自分一人での分析に行き詰まったら、客観的な診断ツールを活用するのも一つの手です。

自己分析で自分の軸が見えてきても、すぐに「これだ!」という天職が見つかるわけではありません。大切なのは、いきなり大きな目標を設定するのではなく、小さな「好き」や「興味」を起点に、まず行動してみることです。
「やりたいこと」と聞くと、何か壮大で特別なものでなければならない、と考えがちです。しかし、その思考法が逆に行動のハードルを上げてしまいます。まずは「少し気になる」「なんだか面白そう」といった、些細な好奇心を大切にしましょう。完璧な答えを探すのではなく、試行錯誤の中から自分に合うものを見つけていく、というスタンスが重要です。
興味の種を見つけたら、次はそれを育てるための小さな行動に移します。リスクを取る必要はありません。今の仕事を続けながらでもできることはたくさんあります。
小さな行動を起こしたら、必ずその結果どう感じたかを振り返り、記録しておきましょう。「想像以上に楽しかった」「意外と自分には合わないと感じた」「この部分についてもっと深く知りたいと思った」など、自分の感情の動きを丁寧に観察します。
この「試す→感じる→記録する」というサイクルの積み重ねが、やがて本当に自分が情熱を注げること、つまり「やりたいこと」の発見に繋がっていくのです。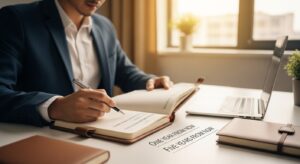
自己分析と小さな行動を通じて得られた気づきを、具体的なキャリアプランへと昇華させていくステップです。ここでの目標は、将来の理想像を描き、そこに至るまでの道筋を具体化することです。
ステップ2で明らかになった「自分の軸(価値観・強み)」と、ステップ3の行動から見えてきた「興味の方向性」。この2つを掛け合わせてみましょう。
例えば、「人の成長をサポートしたい(価値観)」×「教えることが得意(強み)」×「IT分野に興味がある(興味)」という要素が揃えば、「IT研修の講師」や「プログラミングスクールのメンター」といった具体的な仕事の選択肢が見えてきます。このように、複数の要素を組み合わせて、自分だけのキャリアの可能性を探っていきましょう。目指す方向性が定まったら、そこに到達するためのマイルストーンとして、短期・中期・長期の目標を設定します。
一度立てたキャリアパスに固執する必要はありません。目標に向かって行動する中で、新たな興味が湧いたり、価値観が変化したりすることは自然なことです。大切なのは、定期的にプランを見直し、現状に合わせて柔軟に軌道修正していく思考法です。計画通りに進めることよりも、自分自身の成長や変化に対応しながら、後悔のない選択を積み重ねていくことが、充実したキャリアを築く上で最も重要です。

ここまでのステップを一人で進めるのが難しいと感じたら、専門家の力を借りることも有効な選択肢です。第三者の客観的な視点を取り入れることで、自分では気づけなかった強みや可能性を発見できることがあります。
キャリアの悩みは深く、複雑なものです。一人で考え込んでいると、視野が狭くなり、ネガティブな思考に陥りがちです。自分の思考の癖から抜け出し、新たな視点を得るためにも、信頼できる相談相手を持つことは非常に有益です。人に話すことで、自分自身の考えが整理されるという効果も期待できます。
相談先にはいくつかの選択肢があり、目的によって使い分けるのが良いでしょう。
誰かに相談する際は、事前にステップ1や2で整理した自分の考えや悩みをまとめておくと、より有意義な時間になります。「ただ漠然と不安」という状態よりも、「〇〇という価値観を大切にしたいが、今の仕事では実現できず悩んでいる」と具体的に伝えられる方が、的確なアドバイスを得やすくなります。
そして、最終的に決断するのは自分自身である、という意識を持つことが大切です。
「今の仕事にやりがいはない。でも、特にやりたいこともない。それでも転職すべきだろうか?」
この疑問を持つ人は多いですが、目的が明確でないままの転職は、同じ悩みを繰り返すリスクがあります。環境を変えただけで根本的な問題が解決していなければ、転職先でも再び「やりたいことがわからない」という壁にぶつかってしまうでしょう。 一方で、以下のようなケースでは転職を前向きに検討しても良いかもしれません。
「やりたいことがわからない」という悩みは、決してネガティブなものではなく、自分自身の人生やキャリアと真剣に向き合うための大切な転機です。漠然とした不安を抱えたまま日々を過ごすのではなく、具体的な行動を起こすことで、道は必ず開けていきます。
この記事で紹介した5つのステップを、ぜひ一つずつ試してみてください。
A1. 自分一人で強みを見つけるのが難しい場合は、他者評価を取り入れるのがおすすめです。信頼できる友人や同僚、上司に「私の長所や得意なことは何だと思う?」と率直に聞いてみましょう。自分では気づかなかった客観的な強みを発見できることがあります。また、ストレングスファインダー®のような客観的な診断ツールを活用するのも非常に有効です。
A2. 決して遅くありません。30代には、それまでの社会人経験で培ったコミュニケーション能力や問題解決能力といった「ポータブルスキル」があります。この経験を活かしながら新しい専門スキルを学べば、若手にはない独自の強みを持つ人材になれます。いきなり転職するのではなく、まずは副業やオンライン学習など、リスクの少ない方法で小さく始めてみることをお勧めします。
A3. 収入面の不安は大きな壁です。解決策として、現在の仕事を続けながら、やりたいことを「副業」として始めてみるのが現実的です。週末や夜の時間を活用して経験と実績を積み、少しずつ収入を得ることを目指しましょう。収入の見通しが立ち、自信がついた時点で本格的にシフトすれば、リスクを最小限に抑えながら夢に挑戦できます。
記載されている内容は2025年10月23日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。

大学卒業後、または専門学校、高等学校を卒業したあと、就職活動を行うというスタイルが一般的です。ですが、必ずしも就職活動を...

就職活動を始めるにあたって多くの人が何をするかというと、まずどのように就職活動を進めればよいか先輩に聞く、インターネット...

就活において資格は重要になります。しかし、資格がなければ就活が成功しないというわけではありません。資格の中には業務に必要...

就職できなかった大学生はどうなるのでしょうか。新卒採用で就職できた人達は安心して今後の人生が送れます。しかし今の時代、新...

文系にするか理系にするかで悩んでいませんか?大学に進んだ時の苦労、そしてその先の就職するときの苦労など気になることは次か...

履歴書の「趣味特技」欄で採用担当者の心を掴めないかと考えている方もいるのではないでしょうか。ここでは履歴書の人事の...

いまいち難しくてなかなか正しい意味を調べることのない「ご健勝」「ご多幸」という言葉。使いづらそうだと思われがちです...

「ご査収ください/ご査収願いします/ご査収くださいますよう」と、ビジネスで使用される「ご査収」という言葉ですが、何...

選考で要求される履歴書。しかし、どんな風に書いたら良いのか分からない、という方も多いのではないかと思います。そんな...

通勤経路とは何でしょうか。通勤経路の届け出を提出したことがある人は多いと思います。通勤経路の書き方が良く分からない...