
根性がある人の10の特徴・根性がある人になる方法
「根性」とは、一体どのような意味なのでしょうか。また「根性がある人」とは、どのような人なのでしょうか。このページでは「根...
更新日:2025年03月05日
現在、訃報はさまざまな方法で知らされるようになってきています。その際の返信に悩む人もいるでしょう。返信は送ってきた相手のことをしっかり考えて送りたいです。ここでは、訃報に対するマナーから返信の書き方を友人・ビジネス・友達・部下と相手別で紹介します。
目次

まず、「訃報」の読み方ですが、これは『ふほう』と読みます。意味は、不幸があったことに関する連絡です。端的にいうと、亡くなったことを知らせる報告のことです。弔事となるので、もらった際は葬式に参加するためにあわただしくなるということも多いでしょう。
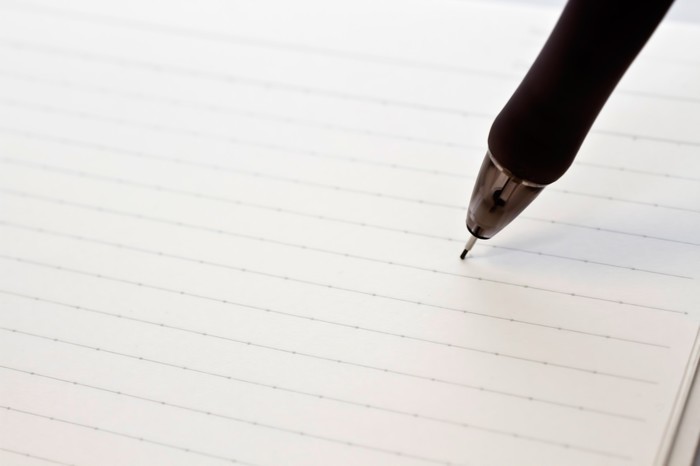
訃報への返信をする際は返信方法に問わず言葉遣いに注意しましょう。特に下記に示したような言葉遣いは避けるようにしてください。
丁寧な文章を心がけるとともに死を彷彿させるような表現は避けましょう。特に遺族に死因を尋ねるのはタブーです。死を彷彿させるような表現の注意点としては、下記のものがあげられます。
訃報というのは基本的に、亡くなったことを手早く端的に伝える文章です。なので、その返信は出来るだけ端的にしましょう。また、長々と書くということはタブーです。そもそも相手から返信がさらに必要になるような文面は相応しくないといえます。
これは、メールでの訃報の返信の場合に限ります。本来メールでの訃報の返信は礼儀的には適切ではありませんが、相手がメールで送ってきた場合は別です。 通常のメールとは違い、「お悔やみを申し上げます」という言葉などを記載し訃報への返信であることを明確にしましょう。氏名を載せるとよりよいです。
これもメールでの訃報の返信の場合に限りますが、絵文字の使用はできるだけ避けるようにしましょう。親しい間柄ならば、可能ですが文字化けする場合や意図が伝わりにくく誤解を生んでしまう可能性もあります。

メールで訃報をもらったときの返信は相手の文面によって大きく違ってきます。畏まった文面であればそれに合わせます。メールというと気軽なイメージがありますが、相当に気を遣ったメールを文面にすることが重要であるといえます。
記載されている内容は2017年05月31日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。

「根性」とは、一体どのような意味なのでしょうか。また「根性がある人」とは、どのような人なのでしょうか。このページでは「根...

カフェやファミレスで気軽に楽しめる一品としてすっかり定番となったピザ。日本では手で持って食べるのが一般的ですが、では、海...

申し送りをする際、どのような事項を伝えればいいのかわからないという人はいませんか。この記事では、申し送りの目的や伝えるべ...

取引先や従業員に贈答品を贈った場合は、経費に計上できるのでしょうか。本記事では贈答品やプレゼントの勘定科目や経費で計上す...
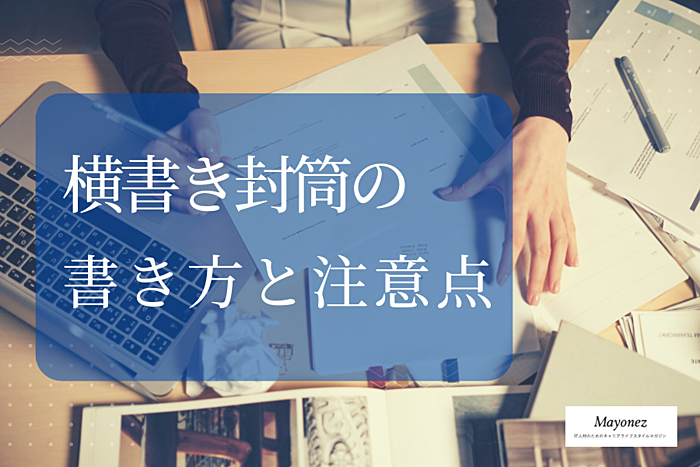
封筒に住所などを横書きするときの注意点をご存知でしょうか。この記事を読むと適切なマナーを守りつつ、一般的にビジネスシーン...

履歴書の「趣味特技」欄で採用担当者の心を掴めないかと考えている方もいるのではないでしょうか。ここでは履歴書の人事の...

いまいち難しくてなかなか正しい意味を調べることのない「ご健勝」「ご多幸」という言葉。使いづらそうだと思われがちです...

「ご査収ください/ご査収願いします/ご査収くださいますよう」と、ビジネスで使用される「ご査収」という言葉ですが、何...

選考で要求される履歴書。しかし、どんな風に書いたら良いのか分からない、という方も多いのではないかと思います。そんな...

通勤経路とは何でしょうか。通勤経路の届け出を提出したことがある人は多いと思います。通勤経路の書き方が良く分からない...