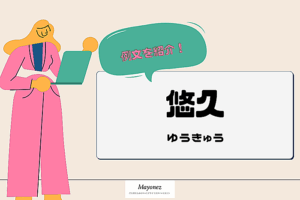
「悠久」の意味や例文を紹介|漢字の語源や「永遠」との違いは?
皆さんは悠久という言葉の響きから、どんな意味のイメージが湧くでしょうか。何かとてつもなく永い年月を思い浮かべるのではない...
更新日:2025年10月30日
ビジネスシーンでメールを作成したり、上司と会話したりする際に「ご教示ください」と「ご教授ください」のどちらを使うべきか迷った経験はありませんか。 この二つの言葉は響きが似ていますが、その語源、意味、含むニュアンス、そして […]
目次


| 項目 | ご教示(ごきょうじ) | ご教授(ごきょうじゅ) |
|---|---|---|
| 教わる内容 | 比較的簡単な知識や手順、方法、一時的な情報 | 学問、技術、芸術など、専門的・体系的な知識やスキル |
| 教わる期間 | 一時的、短時間 | ある程度の期間をかけて、継続的 |
| ニュアンス | 「教えてください」の丁寧語(差し示して教える) | 「師事したい」の謙譲語に近い(学問を教え授ける) |
| 適切な相手 | 上司、先輩、同僚、取引先など幅広く | 大学教授、顧問、その道の第一人者など専門家 |

件名:新しい会計システムの操作方法について(〇〇部 〇〇)
〇〇部 △△様
お疲れ様です。〇〇部の〇〇です。
先日導入されました新しい会計システムについてお伺いしたいことがございます。
大変恐縮ですが、経費精算の申請方法について、具体的な手順をご教示いただけますでしょうか。
お忙しいところ申し訳ありませんが、何卒よろしくお願い申し上げます。
件名:〇〇株式会社の担当者様のご連絡先について
〇〇部長
お疲れ様です。〇〇です。
現在進めております〇〇プロジェクトの件で、〇〇株式会社のご担当者様にご連絡を差し上げたく存じます。
つきましては、ご担当の△△様のメールアドレスをご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

件名:〇〇分野における今後の展望に関するご質問(株式会社〇〇 〇〇)
〇〇大学 〇〇学部
△△教授
突然のご連絡失礼いたします。
株式会社〇〇にて、〇〇の研究開発を担当しております〇〇と申します。
先生の〇〇に関するご論文を拝読し、大変感銘を受けました。
現在、弊社では〇〇の技術応用に取り組んでおりますが、技術的な課題に直面しております。
つきましては、この分野の第一人者でいらっしゃる先生に、今後の研究の方向性についてご教授いただきたく、ご連絡差し上げました。
甚だ勝手なお願いとは存じますが、ご検討いただけますと幸いです。

| 敬語 | 意味 | ニュアンス | 適切な使用例 |
|---|---|---|---|
| ご教示 | 知らない「情報・手順」を教えてもらう | 一時的な情報提供の依頼 | 資料の保管場所を教えてください |
| ご教授 | 専門的な「知識・学問」を継続的に教えてもらう | 体系的なスキルの伝授依頼 | マーケティング戦略をご教授ください |
| ご指導 | 仕事の進め方やあり方など、目的達成のために「導いて」もらう | 実践的な方向性の修正依頼 | 日々の業務についてご指導ください |


記載されている内容は2025年10月23日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。
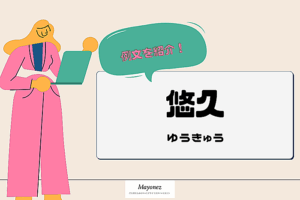
皆さんは悠久という言葉の響きから、どんな意味のイメージが湧くでしょうか。何かとてつもなく永い年月を思い浮かべるのではない...

いまさら意味を聞けないカタカナ語のひとつに、「ビバレッジ」があります。日常生活で使うことは少ないですが、意外と目にする機...

麻雀は世界中で広く遊ばれているテーブルゲームです。古い歴史があるため、麻雀で使う言葉が日常会話で使われることもしばしばあ...

「セパレート」ってそもそもどういう意味?もともと英語の「separate」という単語からきています。もともとの「sepa...

いつのまにか、使われなくなった「父兄」という言葉。なぜ使われなくなったのでしょう。父兄という言葉が生まれた背景とともに考...

履歴書の「趣味特技」欄で採用担当者の心を掴めないかと考えている方もいるのではないでしょうか。ここでは履歴書の人事の...

いまいち難しくてなかなか正しい意味を調べることのない「ご健勝」「ご多幸」という言葉。使いづらそうだと思われがちです...

「ご査収ください/ご査収願いします/ご査収くださいますよう」と、ビジネスで使用される「ご査収」という言葉ですが、何...

選考で要求される履歴書。しかし、どんな風に書いたら良いのか分からない、という方も多いのではないかと思います。そんな...

通勤経路とは何でしょうか。通勤経路の届け出を提出したことがある人は多いと思います。通勤経路の書き方が良く分からない...