
人生ハードモードになる人の特徴7選|原因や抜け出す方法も解説
どういうわけか困難続きだと「自分は人生ハードモードなのではないか?」と思ってしまうことはないでしょうか。本記事では、人生...
更新日:2025年03月05日
借り物競争のルールやお題に頭を悩ませていませんか。この記事では、ルールや進行するポイント、また簡単なお題から面白い、青春を感じられるお題まで様々なものを紹介しています。運動会やレクリエーションなどで企画、運営などをする方は是非チェックしてみてください。
目次
「借り物競争をレクリエーションでやってみたい」
「そもそも、借り物競争ってどんなルール?」
「盛り上がるお題って何だろう?」
このように、借り物競争を企画したものの、どうすれば盛り上がるのだろうかと悩んでいる方もいるのではないでしょうか?
この記事では、借り物競争のルールや、定番のお題から盛り上がるお題、上手な進行のコツを紹介します。
この記事を読めば、借り物競争のルールを把握できます。また、このゲームの肝となるお題についても幅広く用意していますので、是非参考にしてください。更にゲームを進行する上で、大事なポイントもまとめてあります。
レクリエーションを盛り上げたい、参加する人たちを楽しませたい、お題が思いつかなくて困っているという方はこちらの記事をチェックしてください。

借り物競争は、合図と共にスタートし、カードなどに書かれているお題を会場内で誰かに借りて、ゴールを目指す競技です。
細かなルールとして、一度引いたカードは戻すことができません。
単純な徒競走とは違い、走者のスピードだけでなく、簡単なお題を引き当てる運や、お題を持っていそうな人を探す能力なども問われる競技となっています。
スタートは、徒競走と同じで横一列に並び、合図と共に一斉に走り出します。
まずは、お題の書かれたカードを目指し走ります。
スタートラインからそれほど離れてはいない場所にカードがあるので、走力が無い方はここで慌てる必要はないでしょう。
簡単なお題を引けるかは走力ではなく、運です。
自らの運命力を信じましょう。
お題の書かれたカードが置かれているポイントに着いたら、内容を確認します。
違った内容のモノ、人を借りてきた場合、やり直しになるので、落ち着いて確認しましょう。
また、一度引いたカードは戻せない為、注意しましょう。
戻してしまった場合、スタートからのやり直し、または失格になる可能性があります。
もし、戻してしまった場合は、審判の判定に従いましょう。
お題の内容を確認したら、お題に合致する人、モノを探します。
この際に必要なポイントが、目星をつけることと大声の2つです。
まず1つ目の目星をつけることですが、該当するお題に合う人、モノを持っていそうな人を見つける為に必要です。
お題の中には、少しひねったものもあります。
その際にむやみやたらに声を掛けても、ただただ時間が過ぎるばかりです。
年齢層や男女など、そのお題を持っていそうな人の目星をつけることが借り物競争を攻略するポイントになります。
2つ目の大声は、協力者を見つける為に必要です。
お題を誰かに借りなければいけないので、10人に聞くよりも、30人に聞く方が借りられる確率は上がります。
普段、大きな声を出さない人にはハードルが高いですが、借り物競争を勝つ為にやってみましょう。
どの競技でも同じですが、審判の判定には従いましょう。
審判がNGと判定すれば、やり直しになることがあります。
例えば、スタート時のフライングや一度引いたカードを戻すなどはNGに該当します。
判定に従わない場合は、最悪失格となるケースもあるでしょう。
そうなってしまうと会場全体が盛り下がってしまうので、スポーツマンシップは忘れずに競技に参加しましょう。

借り物競争のお題は、ありふれたモノ、借りやすいモノ、ある程度の人が該当する特徴などがあります。
その中で、比較的に簡単で、定番のお題を紹介していきます。
まずは、靴のサイズです。
靴は基本的に皆さんが履いているので該当者が多すぎますが、サイズまで指定すると難易度が少し上がります。
参加者全員が、参加者意識を持てる簡単で定番のお題です。
また、社内でのレクリエーションや、運動靴が指定でない学校などであれば、サイズではなく色を指定するとお題がより複雑化して面白いでしょう。
記載されている内容は2022年10月03日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。

どういうわけか困難続きだと「自分は人生ハードモードなのではないか?」と思ってしまうことはないでしょうか。本記事では、人生...

身近にいるうざい人に悩まされている人もいるのではないでしょうか。この記事ではうざい人の心理や特徴、対処法などについて詳し...

あなたの家族や友人が手術をすることになった時、どんな言葉をかけたらよいか悩んでしまったことはありませんか。本記事では手術...
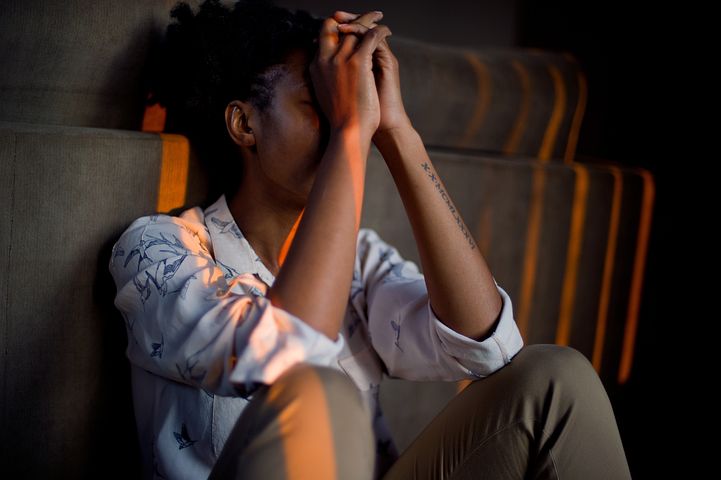
心が荒む時期というのは誰しもがあるでしょう。本記事では心が荒む原因を紹介しています。原因を知ることで、対処法や予防方法も...

香水をプレゼントする意味をご存知でしょうか。本記事では、香水をプレゼントする意味とシチュエーション別の意味に加えて、香水...

履歴書の「趣味特技」欄で採用担当者の心を掴めないかと考えている方もいるのではないでしょうか。ここでは履歴書の人事の...

いまいち難しくてなかなか正しい意味を調べることのない「ご健勝」「ご多幸」という言葉。使いづらそうだと思われがちです...

「ご査収ください/ご査収願いします/ご査収くださいますよう」と、ビジネスで使用される「ご査収」という言葉ですが、何...

選考で要求される履歴書。しかし、どんな風に書いたら良いのか分からない、という方も多いのではないかと思います。そんな...

通勤経路とは何でしょうか。通勤経路の届け出を提出したことがある人は多いと思います。通勤経路の書き方が良く分からない...