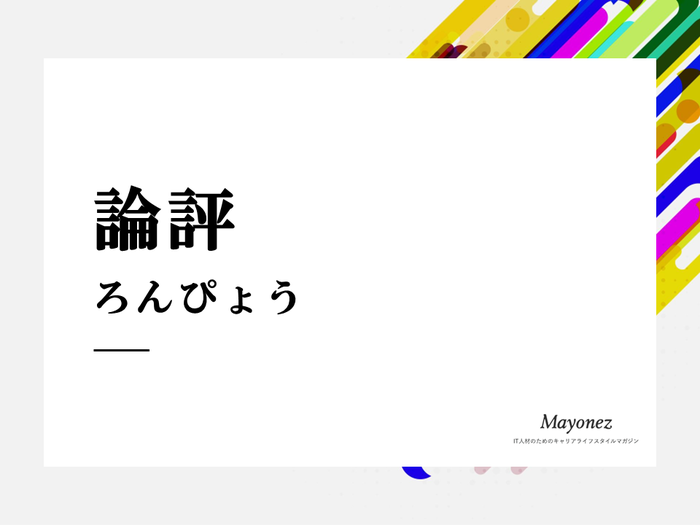[allpage_toc]
「論評の意味が知りたい」
「論評の構成ってどうなっているの?」
「論評の書き方を知りたい」
「論評」に対して上記のような疑問点を持っている方は多いのではないでしょうか。
「論評」という言葉は、新聞などで「政府の経済政策について論評する」や「外交問題を論評する」などの見出しに見られるように、常套的に用いられる言葉になっています。
この記事では、「論評」の意味やその構成要素など深掘りして説明するとともに、論評の書き方や書き出しの際の注意点など紹介します。また論評と似た意味を持つ言葉と違いも紹介しています。
この記事の内容を十分理解していただければ、大学での論文作成などでポイントを抑えた良い論評を書くことができるでしょう。
「論評」について知りたい方は是非ご覧ください。
論評の意味
「論評」とは、ある物事の内容を論じ、批評することを意味しますが、その書き方については「論評」の性格上、慣用的な一定のルールがあります。
このような一定のルールは、「論評」自体の信用性・信頼性を担保するための書き方のポイントを示しています。
ここでは、そのルールについて、項目ごとに説明します。
事象の結果などについて論じること
「論評」は、過去における事象の結果・経緯について、その是非・善悪・優劣などを論じて批評する書き方です。また論述で対象となる結果・経緯について言及し、そこに内在する問題・疑問を指摘してその改善策などを説明したり論じたりします。
このような「論評」は、実際には確かめられていないものを理論的に仮定する「仮説」の論述の仕方とは、意味合いが大きく異なります。
客観的に判断するもの
「論評」は客観的に判断するものであるため、そこにある私見や偏見を排除して、理論的根拠に基づく論理展開やその論理の一貫性に配意した書き方をします。
このような論述の方法により、論評の客観性を確保しつつ、その信用性・信頼性を担保していきます。この点において、自分の感情が露出したり、主観的な目線で話を進めたりする感想文レベルと書き方が異なるところです。
論評の構成
論評では、理論的根拠に基づく論理展開やその論理の一貫性が大切なポイントとなっています。論評の構成にあたっては、このような観点から、しっかりとしたフレームワークを設定し、そのフレームワークの流れの中で論評を書き進めていきます。
ここでは、このフレームワークを「導入」「論評対象の紹介」「論評」に大別して紹介します。
導入
「導入」は、論文の書き方で言えば「序論」の部分にあたり、この部分で論評の対象と背景を説明します。
ここでは、論評の対象とは何かを明示するとともに、そこでどのような問題や疑問があるのか、どのような対策・対応が必要なのかを概略説明し、あわせてこの論評で使われる重要なキー・ワードの定義も示します。
論評の対象の紹介
「論評の対象の紹介」では、論評を読む人の中には全く予備知識がない可能性もあるため、論評する対象である事象・物事などの結果や経緯、関係する事項などについて詳しく説明して、その問題点や論評の核となる考え方を伝えます。
また、論評に関連する論文がある場合は、論文名・論者の名前・主要業績・著書などを紹介します。
論評
「論評」の部分は、論文の書き方で言えば「本論」に相当します。
ここでは、下記のポイントごとに「本論」の中で順次論旨を展開していきます。
・論評の対象とその対象をどのように取り扱うかを論理的背景のもとに提示する。
・論評対象が抱えている問題の現状を示す。必要に応じ対象をいくつかの要素に分類する。
・分析や調査の方法、データ処理の方法を述べる。
・分析や調査の方法に理論的な裏付けがあることを示す。(その理論や学派、代表的な先行研究など)
・分析や調査の結果得られたデータを提示し、説明する。
・分析や調査の結果について解釈し、原因を考察する。
・中心的な問題点や考察の視点を示す。
・一定の前提、条件、仮定のもとに論及する。
・問題点の論及を踏まえ、新たな疑問、問題の視点などを提示して考察を進め、その要点を整理する。
・考察結果、関係理論、先行研究などを理論的根拠として、論者としての判断、主張を述べる。(論評全体の結論)
論評の書き方
論評の書き方については、論評を掲載するジャーナル(学術専門誌)ごとに、そのガイドラインが異なるため、論評を書く際に参考にできる共通の形でルール化されているものはありません。
ここでは、各種ガイドラインに共通する書き方の例などを参考に、その書き方のポイントを紹介します。
このポイントをよく熟読して、質の高い論評を完成させていきましょう。
[no_toc]
1:論評対象の物事の概要を記載する
論評の冒頭では、論評対象の物事の概要を記載する書き方を取ります。
この概要で、論評の対象とは何かを示し、どのような問題や疑問があるのか、どのような対策・対応が必要なのかなど論評の目的を明確に述べます。
概要の文節は、通常の形では一つのパラグラフとなり、独立したドキュメントの性格を持つもので、本論の文節につながるものではありません。
2:批評する点は根拠を持って説明する
「論評」の対象を批評するときは、私見や偏見を排除して、考察結果、関係理論、先行研究などの理論的根拠に基づく論理展開を行ないます。
「論評」は自分自身の立場からの批評であり、単に自分の意見を表明していることを自覚し、読む人に論者の意見・主張を押しつけたり、「それは間違っている」「…すべきだ」など断定的な書き方をしたりすることは避けましょう。
3:筋の通った論理展開をする
論評では、理論的根拠に基づく論理展開とともにその論理の一貫性が大切なポイントとなっています。
膨大な文字数の論述のなかで、首尾一貫した論理を展開することは、その論評の信頼性・信用性を担保する上で大切な書き方になります。
論評の構成にあたっては、このような観点から、しっかりしたフレームワークを設定し、そのフレームワークの流れの中で論理の一貫性をチェックしていきます。
4:論評以外の内容は記載しない
「論評」の中で、関連する書物を批評する際には、批評の対象となる部分以外の内容には触れないようにします。論評以外の内容に触れる書き方は、「書評」のスタイルに近くなります。
「書評」は新刊書などの内容を批評しますが、「書評」によっては、批評にあわせてその書籍の内容全般を紹介する商用目的があるケースも見られます。
「論評」のように限定された対象に対し、批評の根拠を提示した上で論理展開を行うものと比べて、「書評」はその信用性・信頼性に欠けています。
5:自分の意見をまとめた上で書く
「論評」は長大な論述の中で、論者の意見・主張について論理的一貫性を踏まえて記述しなければなりません。このため、事前に自分の意見・主張をまとめて要約した草案をつくり、推敲を重ねて徐々に肉付けしていきましょう。
その都度の思いつきで自分の意見を書いても、論理が破綻したりして何が言いたいか分からない文章の書き方になってしまいます。
6:読む人の存在を意識して書く
「論評」が、たとえすぐれた調査・分析で行なわれたものでも、その文章の書き方が独りよがりのものになったりすると、読む人の心をとらえることができません。
査読をする人も含めて、論評の調査・分析の結果に興味を持つ人がいることを念頭において、分かりやすく丁寧な文章表現でその論旨を書きましょう。
大学の課題などでの論評の書き方のポイント
課題・レポートにおける「論評」は、論文などと違い、ジャーナルのガイドラインに縛られることもなく、ある程度自由度の高いものですが、初めて論評を書くと、ただの「感想文」となりがちです。
ここでは、「論評」が「感想文」とならないための書き方のポイントを説明します。
主観的なことは書かない
文章の中では、「決して…ない」や「いつも…である」などのような主観的な書き方は避けましょう。こうした大げさな表現は、伝えるべきメッセージの内容を散漫にしてしまいます。
また、「その点は間違っている」「…は、こうすべきだ」などと言った断定的な表現の書き方も主観的な要素が前面に出るため、読む人に警戒心を起こさせます。
引用は正しく使う
[no_toc]
「論評」では、他の論者の考えや主張を参考にする場合は、以下の「引用」のルールを踏まえた書き方を必ず守りましょう。
・直接引用:原文や語句をそのまま引用する。引用部分は「」に入れて示す。「」内に変更は加えない。(文中で著者名・著書名などを紹介)
・間接引用:原文の内容を要約したり、言い換えしたりして用いる。(文中で著者名・著書名を紹介)
・文献引用:参照した文献の存在のみを示す。
著者の概要は少なめにする
著者概要は論文構成上必要な部分ですが、著者の概要を長めに書くか少なめに書くかは、査読の評価の対象外と言えます。文字稼ぎの目的で、著者概要を冗長に延ばす書き方には意味がありません。
共著者がある場合は、実際の論文執筆者を筆頭著者とし、加筆修正者を貢献度の高い順に書き、最後にその研究の総責任者を最終著者とします。
論評の書き出しの例
論評に関係する論文がある場合は、その論文名・論者の名前・主要業績・著書など「Academic Biography(研究者プロフィール)」を紹介する書き方が一般的になっています。
以下に、その書き出しの例を紹介します。
1:著者の出身地の紹介
「Academic Biography(研究者プロフィール)」では、上述のプロフィールに加えて、趣味、出身地、住んでいる街、家族構成、ペットなど個人的なものにも触れます。とりわけ、同郷意識の強い日本では、著者の出身地の紹介は欠かすことができません。
このようなプロフィールでは、論評を読む人に著者の人となりが伝わるよう、端的な表現を使いましょう。
・この著者は〇〇県の出身で、緑豊かな自然で育った筆者の幼児体験が、その後の生物学者への道を開いた。
2:論文などの誕生の経緯を記載
論評に関係する他の筆者の論文を紹介する場合、その論文の誕生経緯に触れる書き方もあります。
この場合、紹介冒頭で、論文の誕生経緯に触れ、その論文が学問的に公知された必然性(時代的背景・社会的背景・先行研究への批判など)を簡潔に説明します。
・引用させていただいた論文は、著者が長年のライフワークであった〇〇研究をもとに…
3:自分の感想を述べる
上述の他の論文の紹介にあわせて、自己の論評との関係性から、その論文の著者の見解、主張を肯定的または否定的に取り上げて評価を与え、その後の議論につなぎます。
この際、自分の感想・主張を裏付ける客観的な根拠も明記することを忘れてはいけません。
・先行研究の論点をまとめると、……のようにまとめられる。しかし、その見解については……という点で検討の余地がある。
4:著者・論者の概要を述べる
論評に関係する論文の著者や論者については、その見解、主張の大要を紹介するとともに、その論旨に対する自分の判断や主張を述べましょう。
このような自分の判断や主張の部分は、学術的に認知されている理論・先行研究・自分の調査分析結果などを踏まえて行ないます。
・著者は、この論点について概要説明すると、……は、……という有用な見解を示している。この見解は、……に関する先行研究でも同様な見解を踏まえており、……の観点から、その論旨は妥当と考える
論評と似た意味を持つ言葉との違い
「論評」という言葉は大まかな意味で「あるものごとの内容を論じ、批評すること」を表し、意義の類似する語群としては、「書評」「講評」「感想文」などがあります。
ここでは、「論評」とこれらの類義語との違いを見ていきます。
論評と書評
[no_toc]
「論評」の対象は書物や論文・政治問題や経済状況など多岐に渡り、そこに内在する問題点・矛盾点などを論理的手法で指摘し、その解決・改善策など論じますが、「書評」は、その対象は書物だけで、そこに記載されている主張や考え方を論じ、批評することを指します。
また、「書評」の場合、時には、対象の書物の批評にあわせて、その書物を薦める役割を担う「商用的な意図」も含まれる場合があり、このような点で「講評」との違いがあります。
論評と講評
「論評」と「講評」はともに理論的根拠をもとに論理展開するものですが、「論評」をする論者の立場には身分上・立場上など一切の制約はありません。
これに対し、「講評」では、身分上・立場上から指導的立場にある論者が対象となる論文・作品・演技などの出来映えを批評し、その論点などを説明します。
このような「講評」は学術的に公知されることが前提にあり、「査読(論文などの内容を審査するために読むこと)」とは意味合いが異なります。
論評と感想文
「論評」の対象は書物や論文・政治問題や経済状況など多岐に渡り、その選択肢に制約はありません。その書き方については、「論評」自体の学術的な信用性・信頼性を担保するため、慣用的な一定のルールが存在します。
これに対し、「感想文」は、大学などでの受講内容に沿った書き方が求められます。その書き方については特段の制約なく自由な形式で書くことができ、自分が感じたことや主観的な判断を盛り込むこともできます。
論評は書き方のポイントを押さえて正しく書こう
「論評」では、その「論評」自体の学術的な信用性・信頼性を担保するため、論評の構成・書き方、研究の対象・背景、先行研究の提示、研究目的・研究行動などの論述について、詳細なルールが存在します。
そこでは、論拠の根拠となるもののオーサーシップ(原作者、著作者、出所など)を明らかにするとともに、論評の論述のオリジナリティーを確保することが求められています。
論評を書く際には、論評のオリジナリティーとオーサーシップに配意しながら、上述した書き方のポイントを押さえた正しい論述に努めましょう。