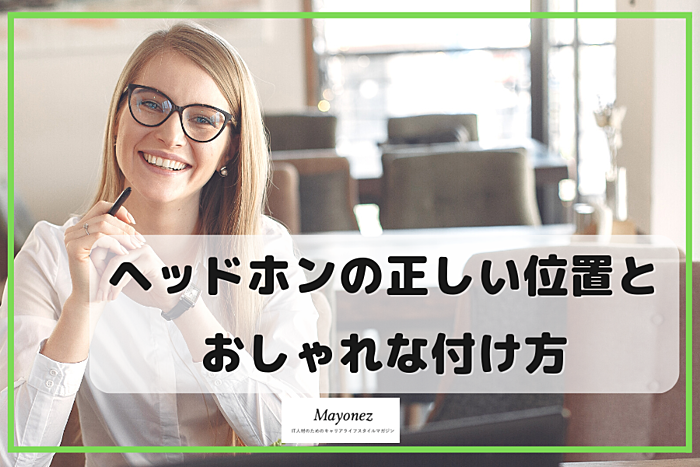[allpage_toc]
「種類によってヘッドホンはどう違う?」
「おしゃれにヘッドホンを取り入れたい時の選び方が知りたい」
「帽子やメガネを付けたまま使えるヘッドホンはある?」
電車の中などの移動中や、自宅で音楽を楽しみたい時に、ヘッドホンを利用したいと考えたことはありませんか。
この記事では、ヘッドホンの形状や仕様の種類について解説し、選び方のポイントについて紹介しています。これまで自分のヘッドホンに満足できていなかった人は、この記事を読むことで自分に適している物の条件が具体的に判断できるようになるでしょう。メガネや帽子など、おしゃれの中に溶け込むヘッドホンの付け方もわかります。
より音楽ライフを充実させたい人は、ぜひこの記事を参考に自分に合ったヘッドホンを選んでみてください。
バンドの構造によるヘッドホンのタイプ
バンドの構造による大きな違いは、ヘッドホンの装着の仕方が変わることです。大きく2種類に分けられるので、それぞれの特徴について見ていきましょう。
主流のオーバーヘッド型
ヘッドホンと聞いて誰もがイメージする形状がオーバーヘッド型です。パーツ構成は、装着時に頭にフィットさせるヘッドバンドと、左右のスピーカーボックスとなっています。ドライバーユニットのサイズが大きく、高音質が持ち味のヘッドホンです。
バンドが後ろにくるネックバンド型・バックバンド型
オーバーヘッド型の次に多いとされるのがネックバンド型・バックバンド型と呼ばれるものです。後頭部にヘッドバンドを回すように装着します。
耳の上部や首、後頭部でホールドされるため、セットした髪型が乱れるなどの心配がなくなり、動き回っても装着感が安定しているのが、このタイプのメリットです。ただし、オーバーヘッド型よりも小型で軽量ではありますが、締め付けが強くて長時間の使用に向かないというデメリットも存在します。
耳を覆うかどうかによるヘッドホンのタイプ
ヘッドホンの種類は、バンドの構造以外にも耳を覆うかどうかでタイプ分けができることをご存じでしょうか。タイプの違いが使用時にどう影響するのか、詳しく見ていきましょう。
音漏れの少ないオーバーイヤー型
耳全体をすっぽりと覆うタイプのヘッドホンは、オーバーイヤー型と呼ばれます。外部からの音が遮断されて、音漏れが少なくなるというメリットがあり、音質にも優れているのが特徴です。
ただし、耳を完全に覆うだけのサイズが必要になるため、大型で重くなりやすいのがネックとなります。
装着感の軽いオンイヤー型
オンイヤー型は、耳の上に乗せるイメージで装着するヘッドホンです。音質的にはオーバーイヤー型の方が有利ですが、コンパクトで軽量であるのが最大のメリットとなります。
比較的手頃な価格で入手でき、ファッション性の高い物も多くあるタイプです。
[no_toc]
ハウジングの構造によるヘッドホンのタイプ
ヘッドホンのハウジングとは、音を出すドライバーが入った耳を覆うイヤーカップ部分のことです。外観・耐久性・音質の3つは、この部分からの影響を強く受けるため、ヘッドホンを選ぶ際には重要なポイントになってきます。
遮音性の高い密閉型
音を発する振動板の背面と耳までの空間の両方が密閉されているハウジング構造の物は、密閉型、もしくはクローズド型と呼ばれるタイプです。
高い遮音性と細かい音の解像度の高さによる力強い重低音が楽しめます。その一方で音がこもりやすくなるため、立体感や臨場感などの表現を苦手としています。
臨場感がある開放型
ハウジングの構造が、振動板の周囲の空間がまったく密閉されていないタイプは、開放型、もしくはオープンエアー型と呼ばれます。自由な空気の出入りによって開放的な音質となるのが特徴です。
音がこもらずクリアな高音が楽しめ、長時間の視聴に適している反面、低音が弱くなり音漏れの大きさが問題点となります。
程よい臨場感と重低音を楽しめる半解放型
一般的とは言えませんが、半開放型、もしくはセミオープン型と呼ばれるタイプも存在します。定義が曖昧なタイプであるため、密閉型と開放型を足して2で割った感じと言えば、わかりやすいでしょう。
半開放型に該当するのは、密閉型構造のハウジングに孔を空けたタイプと、振動板の一部の側面を遮断した開放型タイプです。重低音の表現力は高いけれど密閉型ほど音はこもりませんし、音漏れはあるものの開放型よりは遮音性が期待できる物が多くあります。
有線か無線かによるヘッドホンのタイプ
ヘッドホンといえばコードとプラグが付いているのが当たり前だったのですが、近年の無線技術の発達により、それらを必要としないヘッドホンも登場しています。
有線と無線でどう違うのか、それぞれについて見ていきましょう。
快適なワイヤレス型
コードレスタイプのヘッドホンはワイヤレス型と呼ばれる物になり、外出先で使用する時にコードが絡まるなどの煩わしさから解放されるのが魅力です。ただし、快適に視聴できる一方で、電池が切れてしまうと使用できなくなってしまうという問題があります。
近年でBluetoothの改良が進み、いろいろな機種と簡単に接続できる点と音質の改善された影響で、大きくシェアが伸びてきているヘッドホンです。
音質面で有利な有線型
[no_toc]
ヘッドホンの基本となるコードのある有線型は、いろいろなモデルで商品展開がされているため、低予算でも入手できるものがある選択肢の広さが特徴です。
ワイヤレス型と違い、音楽再生機器からの音質劣化が少なくなるため、音の遅延や途切れがなく、常に高音質で音楽が楽しめます。充電切れを気にする必要がなくなるのも、有線型の魅力です。
ヘッドホンの正しい付け方
ヘッドホンを装着して、頭痛や肩こり、耳が痛くなったという経験はありませんか。正しい付け方をすることで、これらのリスクは減らすことができます。
まずは、ヘッドホンの正しい付け方を知って、これまでの自分の付け方を見直してみましょう。
ヘッドバンドの位置は頭頂部・スライドで軽くフィットさせる
ヘッドホンの正しい位置は、ヘッドバンドが頭頂部で軽くフィットし、耳に圧迫感がなく、音漏れもしない程度に付け心地のよい場所です。
まずは、基本位置となる頭頂部の真ん中にヘッドバンドを付けるのがポイントになります。そこから、左右のスライドで上下を調節しながら、全体が軽くフィットする位置を探していきましょう。
イヤーパッドは耳全体を覆う位置に
耳に当てる部分となるイヤーパッドは、耳全体を覆う位置に持ってきましょう。イヤーパッドが少しでもズレていると耳の側面が痛くなる可能性があるので、重要なポイントと言えるでしょう。
大抵のヘッドホンで、イヤーパッドは少し動かせるようになっています。左右のスライドで高さについても微調整を行い、適切な位置にイヤーパッドを置きましょう。
ヘッドホンの左(L)と右(R)を間違えない
意外と知られていませんが、ヘッドホンは左右で出ている音が違っています。右からは楽器の音、左からはボーカルの声が聞こえるといったイメージだとわかりやすいでしょう。
ヘッドホンの左右の付け間違いは、上手く音が拾えなくなったり、ノイズが混じったりする原因の1つに挙げられます。一度反対にしてみると、はっきりとした違和感を覚えるので、気になった人は試してみてください。
宝飾品やアクセサリーは外す
ヘッドホンを装着する時は、ピアスやイヤリングなどの耳に付ける宝飾品やアクセサリーは外すのが基本です。
ヘッドホンの使用中には気にならなくても、外した後で耳が痛んでくる場合があります。また、ピアスの先などでヘッドホン自身を傷つけてしまうことも考えられるでしょう。
自分に合うヘッドホンの選び方のポイント
種類の多さと価格帯の広さから、選び方のポイントを押さえていないと自分に合うヘッドホンを見つけるのは、かなり困難でしょう。
以下で紹介する7つのポイントを理解して、自分にとってどんなヘッドホンがベストなのか絞り込んでみてください。
- 耳・頭・顔とサイズが合っていること
- 使う目的に合う形や構造を選ぶ
- 使う場所を考える
- ヘッドホンのデメリットを理解して選ぶ
- 好きな音楽のジャンルに合わせる
- 重さをチェックする
- 実際に装着してみる
[no_toc]
耳・頭・顔とサイズが合っていること
ヘッドホンのサイズが耳・頭・顔と合っていないと、正しい付け方をしていても耳の側面や頭が痛くなります。
サイズが合うかどうかを確かめるには、購入前に家電量販店などで実際に装着してみるのがおすすめです。最終的にオンラインで購入する場合であっても、失敗しないヘッドホン選びの作戦の1つとして、ヘッドバンドがきつくないかなどチェックしてから購入を決めましょう。
使う目的に合う形や構造を選ぶ
ヘッドホンは用途別に分けることができ、モニターヘッドホンとリスニングヘッドホンの2つがあります。
モニターヘッドホンは、忠実に原音が再現されるのでレコーディングなどの音楽制作現場に最適なタイプです。
一方、リスニングヘッドホンは、耳に馴染みやすく音に味付けがされているのが特徴です。低音ブーストが入っている物など、それぞれで音質に違いがあります。気軽に音楽やゲームの音を楽しむのにおすすめです。
自分がどんな目的でヘッドホンを使いたいかでモニターヘッドホンかリスニングヘッドホンを選び、その上で形や構造を選んでいきましょう。
使う場所を考える
実際にヘッドホンを使いたい場所を考えることで、どんな機能が付いている物が良いのか判断できるようになります。
例えば、通勤や通学中なら遮音性の高い物や、ノイズキャンセリング機能が入った物の方が良いでしょう。ジョギングやエクササイズ中なら、激しい動きをしてもズレにくく雨や汗に強いネックバンド型がおすすめとなります。
ヘッドホンのデメリットを理解して選ぶ
上述してきたとおり、ヘッドホンのタイプは複数あり、それぞれにメリットとデメリットがあります。
例えば、音質を重視してオーバーヘッド型を選べば、持ち運びにくさがデメリットとなります。逆に、持ち運びやすさを重視してオンイヤー型にすれば、音質が少し劣化し、長時間の装着で耳を痛めやすくなるリスクが高まるでしょう。
全てに納得のいくヘッドホンを選ぶのは難しいため、あらかじめデメリットを把握した上で選びましょう。
好きな音楽のジャンルに合わせる
好きな音楽のジャンルに合わせて選ぶのもおすすめです。
普段聞く音楽のジャンルが、ロックやポップス、アニソンなどなら、メリハリの聞いた躍動感がある音を楽しめる密閉型が良いでしょう。また、ジャズやクラシックなら楽器の繊細なニュアンスや空気感が表現できる開放型が最適となります。
重さをチェックする
ヘッドホンは種類によって重さが大きく違っているため、重さが何gなのか確認しておく必要があります。
基本的に重い物の方が首や肩への負担が大きくなるため、なるべく軽い物を選ぶのがおすすめです。特に、外出時に便利なタイプは持ち運びのしやすさも重視しているため、軽くて遮音性の高い物が多くなっています。
実際に装着してみる
自分に合っているかどうかをチェックするのに特に適している方法が、店頭でヘッドホンを実際に装着してみることです。
耳への圧力や実際の音質など、直接体験してみると多くのことがわかります。特に、装着した時のフィット感と見た目は、自分自身で試してみないとわからないものです。
見た目はすごく好みだけど、使い心地はイマイチという場合もあります。店頭でいろいろな観点からヘッドホンの試着と比較を行い、自分に合ったヘッドホンを探すのがベストでしょう。
ヘッドホンで耳や首・頭が痛くなる原因
音楽好きの人には欠かせないヘッドホンですが、正しい付け方を実践しているにもかかわらず、耳や頭などに痛みを覚えることもあるでしょう。5つを紹介するので、自分に当てはまるものがないかチェックしてみましょう。
[no_toc]
- サイズが合っていない
- 重い
- 大音量や質の悪い重低音
- 長時間の使用
- メガネとヘッドホンの組み合わせの悪さ
サイズが合っていない
頭とヘッドホンのサイズが合っていないと、正しい付け方でも圧迫感を覚えやすくなり、頭痛などを引き起こします。
もしヘッドバンドの跡が付いているなら、締めすぎによる圧迫感が強いサインです。特に、使っているヘッドホンが密閉型なら、イヤーパッドからの音漏れ対策のためにヘッドバンドをキツく締める仕様になっている場合があるので確認してみましょう。
重い
付け方が正しくても、ヘッドホンが重いと頭痛や首の疲れ、肩こりの原因になります。
ヘッドバンドが二重になっている物なら、なおさらずっしりと重みを感じるでしょう。重いヘッドホンを長期間付けていたせいで、抜け毛や髪のすり減りがひどくなったという人も、中にはいます。
大音量や質の悪い重低音
正しい付け方をしているのに耳や頭が痛くなる原因には、音量と音質も含まれます。
コンサートなどで響く大音量が原因で、突然頭痛に襲われたり、気分が悪くなったりした経験はありませんか。これは質の悪い重低音による低音酔いと呼ばれる症状です。また、大音量で長時間視聴することで症状が悪化し、最悪イヤホン難聴になる可能性もあります。
長時間の使用
耳の内側に鈍い痛みを感じるなら、長時間ヘッドホンを装着していることが原因となっている可能性があります。肩や首のコリや頭痛にもつながるので注意が必要です。
同じ場所に圧力がかかり続けるのが問題なので、適度にヘッドホンを外して休憩を挟んだり、こまめに位置を少しズラしたりするよう気をつけましょう。
メガネとヘッドホンの組み合わせの悪さ
メガネとヘッドホンを同時に装着する人もいるでしょう。その際に、耳にかかっているメガネのテンプルがヘッドホンに押し付けられることで痛む場合があります。
この状態のままヘッドホンを使い続けると、痛み以外にもメガネが歪む結果につながってしまう恐れがあります。一度ヘッドホンを外して耳を休ませる必要があるでしょう。
ヘッドホン使用時の痛みを和らげるコツ
せっかく高級なヘッドホンを購入したのに自分に合っていないせいで痛みが発生しても、買い替えに踏み切れない人も一定数いるでしょう。そんな場合には、これから紹介する使用時の痛みを緩和する方法を試してみるのがおすすめです。
- ヘッドホンをストレッチさせ馴染ませる
- ヘッドバンドにクッションを加える
- 柔らかい耳あてパッドに変える
- 適切な音量で聞く
- 長時間の装着を避ける
[no_toc]
ヘッドホンをストレッチさせ馴染ませる
新品もしくは締め付けがキツイ場合は、ヘッドホンをストレッチ(広げる)させると馴染むようになります。
やり方は、頭と同じくらいの本や箱などを使って一晩おいておくだけです。それでも締め付けがキツイなら、もう少し長い時間をかけましょう。ただし、やり過ぎると緩くなってしまうので注意が必要です。
ヘッドバンドにクッションを加える
別売りになりますが、ヘッドバンドに付けるクッションを利用するのも効果的です。
購入前に自分のヘッドホンに対応しているかの確認と、カラーバリエーションも多いとは言えない点に注意が必要ですが、大抵テープやマジックテープで簡単に付けられます。痛みが耳と頭の両方に及ぶ場合におすすめです。
柔らかい耳あてパッドに変える
耳が痛くなる原因がイヤーパッドの固さにあるなら柔らかい物に変えるという選択肢があります。
ただし、この方法は耳への負担が改善されるものの、音質や見た目が変わるなどのデメリットが発生します。不安が大きい場合には、自分の耳に合う他のヘッドホンを改めて購入する方が良いでしょう。
適切な音量で聞く
ヘッドホンによる痛みの原因でも触れましたが、大音量での視聴は難聴になる危険性があります。また、音量が大きすぎると他の音が聞こえにくくなる点にも注意が必要です。
大音量により耳を傷つけてしまっては、好きな音楽も楽しめなくなります。大音量の気持ちよさを感じたい人もいるでしょうが、自分の耳を大事にすることが第一です。
長時間の装着を避ける
少しでもヘッドホンの使用中に耳が痛いと感じたら、一度取り外して休憩を取りましょう。
どんなヘッドホンであっても、長時間の使用は重さや圧迫感からのダメージが蓄積されていきます。1時間を目安に休憩を入れることで、耳が痛くなりにくくなるだけでなく、難聴も防止できるようになるのでおすすめです。
メガネをかける時のヘッドホンのかっこいい付け方
基本的に、ヘッドホンを先に装着してからメガネをかける付け方がおすすめです。左右のスライド部分の隙間からメガネを通しましょう。イヤーパッドの上部にメガネのフレームが乗ることでメガネが固定されて、耳が痛くなることも避けられます。
ネックバンド型・バックバンド型を使う
上述した付け方でも痛みが気になる場合は、ネックバンド型・バックバンド型のヘッドホンを使ってみましょう。もしくは、耳にイヤーフックをかけて使う耳掛け型と呼ばれる小型ヘッドホンを検討してみても良いでしょう。
どちらも頭の上からヘッドバンドがなくなることで圧迫感が少なくなり、メガネと併用しやすくなります。
テンプルが柔らかいメガネを使う
[no_toc]
ヘッドホンではなくメガネを工夫する方法もあります。仕事などでメガネとヘッドホンの両方を長時間付ける必要がある場合は、特におすすめです。
一般的なメガネは、テンプルを柔らかい素材にしたり、太めのデザインにしたりすることで、頭に食い込みにくくなります。しかし、買い替えが難しい場合はテンプルに市販のパッドを付けるだけでも負担が軽減できます。
また、テンプルを耳に引っ掛けないヘッドホン用メガネに買い換えるという選択肢もあるので、検討してみてください。
帽子に合うヘッドホンの可愛い付け方
ヘッドホンで音楽を楽しみながら、帽子によるファッショ性も両立させたいと悩む人は、一定数いるでしょう。帽子の種類に合わせたヘッドホンの付け方を紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
キャップの場合は上からヘッドホンを付ける
ボーイッシュな印象を与えるキャップと組み合わせる場合は、キャップの上にヘッドホンを付けましょう。華奢な女性なら、ゴツめで大きいヘッドホンにすることでギャップが生まれて、男性からモテる場合もあるでしょう。
ヘッドバンドを少し前後にずらすと、DJやストリートファッションのようなテイストになります。逆ストリート系ファッションにしたいなら、ツバが真っ直ぐなキャップを選ぶのがポイントです。
ニット帽は耳の上までかぶり上からヘッドホンを付ける
ニット帽を先にかぶり、その上にヘッドホンを付けるという順番がポイントです。しっかり音を拾いたいのなら、ニット帽の位置を耳の上程度までにしましょう。
シンプルな色合いのヘッドホンを選ぶと、ニット帽が際立って可愛く見せられます。ちなみに、ヘッドホンが目立つのを避けたい場合は、ニット帽で耳を覆ってからネックバンド型を付けるのがベターです。
ハットはバックバンド型やネックバンド型のヘッドホンがよい
紳士的なハットと組み合わせるなら、ネックバンド型・バックバンド型のどちらか、もしくはイヤホンがおすすめです。
特にオーバーヘッド型とハットの相性は悪く、順番に関係なく付けにくさがネックとなります。仮にツバを折り曲げて付けたとしても、ヘッドホンが横に広がるせいで不格好でしょう。ただし、横に広がるタイプのハットなら、先に小さめのヘッドホンを装着し、すっぽりとハットで覆うという付け方ができます。
髪型が崩れないおしゃれなヘッドホンの付け方
せっかくセットした髪型がヘッドホンで崩れるのを避けたいなら、ネックバンド型・バックバンド型のヘッドホンがおすすめです。バンド部分が頭頂部ではなく後頭部に来るため、ロングヘアーやワックスで決めた髪型に干渉することがありません。
ちなみに、ヘッドホンによる見た目のインパクトがなくなっても構わないなら、イヤホンにするのも良いでしょう。